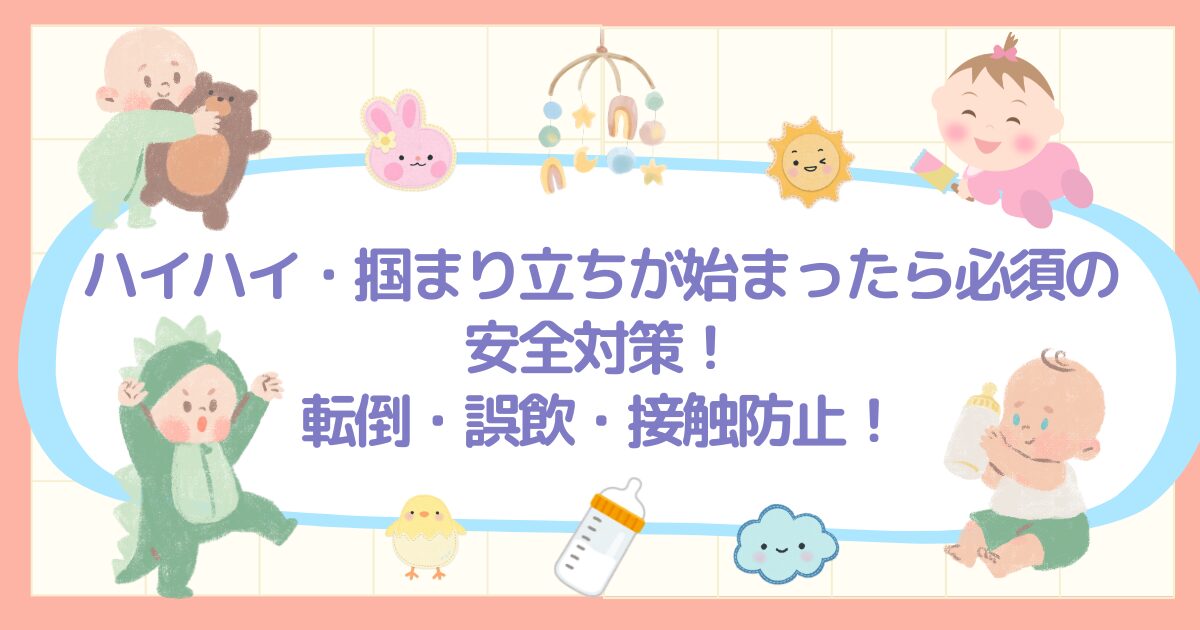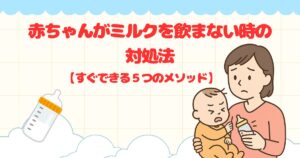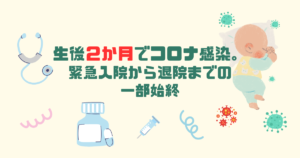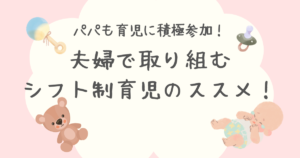こんにちは!なぎびです。
8か月を過ぎるころになると、赤ちゃんはハイハイもできるようになり、急激に、いろんなところに移動できるようになります。
9か月にもなれば、つかまり立ちが始まる赤ちゃんもいます。部屋の中を縦横無尽にハイハイで歩き回る姿は、とーーーーーってもかわいいですが、その半面、なかなか目が離しづらくもなるのも、悩ましいところです。
また、おもちゃだけでなく、さまざまな日用品、ママやパパの髪の毛や耳、目などの体の一部の他、メガネや着ている服のチャック、ボタン、ワッペンなど、いろいろな物に興味を示して、さわったり、お口で咥えたり、なめたりします。
ちょっと目を離した隙に、何かに頭をぶつけたり、挟まれたり、飲み込んでしまったりと、今まで以上に、いろんなことに気を付けなければなりません。
赤ちゃんが、安全にすくすく成長するために、未然に、しっかりと安全対策をしましょう!
この記事では、
- ハイハイを始めたけど、どんなことに注意すればいいの?
- ちょっと目を離した隙に移動して、いろんなものに触って困っている。
- 掴まり立ちを始めたけど、よく転ぶのでケガをしないか心配。
などについて、私が実際に行っていることや使ってよかったものなどを紹介します。
ハイハイ・掴まり立ちが始まったら必須の安全対策
まず初めに、ハイハイや掴まり立ちを始めた赤ちゃんにとって、家の中には、どんな危険が潜んでいるでしょうか?まずは、いわゆるKY(危険予知)で、危険を洗い出してみると、例えば以下のような危険が潜んでいます。
- 段差や階段から転げ落ちるかもしれない。
- タンスや机の角に、頭や体をぶつけるかもしれない。
- 扉や引き出しに手や指を挟むかもしれない。
- 小物やゴミ、床に落ちた食べ物などを飲み込んでしまうかもしれない。
- 熱くなったストーブやファンヒーターに触れて火z傷するかもしれない。
- テレビなどに触れた拍子に、倒れてきて下敷きになるかもしれない。
- 机の上の花瓶、本棚の本が倒れて、落下してくるかもしれない。
- ガラス製品が倒れたり、落下したりして、割れたガラスでけがをするかもしれない。
- ひざ掛けや毛布が覆いかぶさって窒息するかもしれない。
- etc…
このように、家の中には、たくさんの危険が潜んでいることがわかります。これらは、あくまで一例ですので、考えれば、もっとたくさんの危険が見つかるかもしれませんし、それぞれの家庭のお部屋の状況によっても変わってきます。
一度、自分の家の中を見回して、赤ちゃんにとって危ない場所や物がないか確認してみましょう。
※うちでは、結婚記念にもらったペアのワイングラスを本棚に飾っていたのですが、模様替えをしようとちょっと棚を動かした途端に、落下して粉々に割れてしまいました。運よく、そこに赤ちゃんがいない時だったのでよかったですが、もしその場にいたらと考えると、ぞっとします…
では、赤ちゃんがお家で安全に過ごすためには、どうすればいいでしょうか。赤ちゃんを危険から守るためには、以下の3つのことが大切です。
- 危ない場所・物をなくす。
- 危ない場所・物に近づかせない。
- 危ない場所・物に対策をする。
では、赤ちゃんにとって危ない場所・物とは何でしょうか。それは、KYで出てきた危険の原因となった場所や物のことです。
危ない場所の例・・・段差・階段・ソファ(落下・転倒の危険)、フローリング・床の凹凸(転倒の危険)、ドア・家具の引き出し・椅子などの稼働部分(挟まれの危険)、家具のかど・金属部分(打撲の危険)、暖房器具(火傷の危険)、コンセント(感電の危険)など
危ない物の例・・・ガラス製品・針・ペン・棒状の物・ホチキスの芯(刺さる危険)、ハサミ・カッター(切れる危険)、おはじき・錠剤・ゴミ・ティッシュ・ヘアゴム・リップクリーム・口紅・消しゴム・タバコ・吸い殻などの口に入る小さな物(誤飲の危険)、コード類・ヒモ類・薄手の布製品などの巻きつく物(窒息の危険)、電池・薬・タバコなど有害物質を含む物(有毒の危険)など
これら以外にも、私たち大人にとっては、日頃から使っている当たり前の物でも、赤ちゃんにとっては、新鮮で興味をそそられるものがたくさんあるはずです。それらに危険が無いか、赤ちゃんの目線に立って、よく検証することが大切です。
では、それらの危険を防ぐための①②③の対策を次にご紹介します。
①危ない場所・物をなくす。
まずは、赤ちゃんの周りにある危険で、なくせるものなくしてしまうことからはじめましょう。具体的な対策は、以下のようなものです。
※忙しい毎日の中で、ついうっかり、自分が使っている日用品を置きっぱなしにしてしまうことがあるかもしれません。普段から使うものや小物などは、あらかじめ、赤ちゃんの手の届かない場所に、置き場所を決めて置き、必ずそこに置くように気を付けましょう。
②危ない場所・物に近づかせない。
なくすことができないものもたくさんあるので、①の次は、赤ちゃんを危ない場所や物に近づけさせない工夫をすることになります。
- ベビーサークルで、赤ちゃんの自由に移動できる安全なエリアを作る。
- 階段や段差、ドア、暖房器具などの危険な場所や物に、柵やパーティション、ベビーゲートなどで部分的に近づけないようにする。
③危ない場所・物に対策をする。
①のなくすこと、②の近づけさせないことのどちらも難しい場合は、ピンポイントで、対策をする必要があります。
赤ちゃんとずっと一緒にいて、見ていてあげれれば一番いいのですが、掃除、洗濯、ミルクや離乳食の準備、オムツなどのゴミの処理、お風呂の準備など、どうしても、目が離れてしまうタイミングはあるので、そういった時でも、安心できるように、日頃からしっかりと対策をしておきましょう!