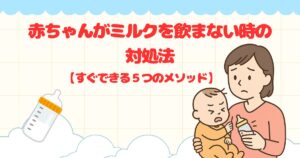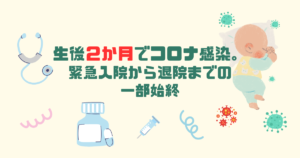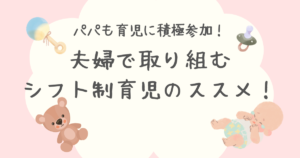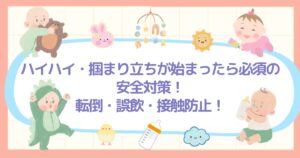こんにちは!なぎびです。
最近では、男性の育児休暇取得について、ニュースなどでもよく取り上げられるようになってきました。育メンなんて言葉も、よく聞きますね。
ひと昔前(昭和?)は、男性は外で働いて、女性は家を守るといった考えが主流であったため、必然的に、育児や子育ても、女性がするのが当たり前といった考え方が根強くありました。
しかし最近では、社会の変化や働き方の多様化などによって、女性も積極的に社会参加やキャリアアップが図れる世の中に変わりつつあり、男性と女性がより平等な社会の実現に向けて、様々な取り組みがなされています。
そのような流れの中で、男性の育児参加もかなり浸透してきており、男性の育児休暇取得は、国も後押ししています。
この記事では、
- 赤ちゃんが生まれたけど、男性でもちゃんと育児できる?
- 男性の育児休暇制度ってどんな制度?
- 育児休暇は取得したいけど、取っても大丈夫?
といった疑問にお答えします。
絶対とるべき!パパが育休を取得すべき5つの理由
もしパパの勤め先に、男性の育児休暇制度があるのであれば、赤ちゃんが生まれたら、絶対に取得すべきです。その理由は、以下のとおりです。
- 産後のママには、パパの助けが必須
- 赤ちゃんとの絆の形成につながる
- 会社・社会の評価が向上する
- 人生を見直すいい機会になる
- お金に代えがたい貴重な時間が得られる
産後のママには、パパの助けが必須
まず、もっとも大切なことは、産後で体力が落ちているママを助けることです。出産は、交通事故で全治 3 か月の大けがを負うのと、同じくらいのダメージを受けると言われています。また、体が元通りになるまでには、数か月、長ければ1年以上かかる場合もあります。
そのような状態の中で、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話や家事をするのは、本当に大変です。通常の家事に加え、授乳、おむつ替え、沐浴、抱っこ、寝かしつけ、お着替えなどの赤ちゃんのお世話に、休む暇も十分寝る暇もなく対応しなければなりません。
また、慣れない育児で、常に気が張っていて、精神的にもきつくなってしまう場合も少なくありません。
赤ちゃんは、2人の大事な大事な宝物ですから、2人で育児に取り組むべきです。パパも積極的に家事や育児に参加して、産後で大変なママを支え、協力して育児に取り組むためには、パパの育児休暇取得は絶対必要です。
赤ちゃんとの絆の形成につながる
パパが育児休暇を取って、赤ちゃんのお世話を積極的に行うことで、赤ちゃんとのスキンシップや赤ちゃんと関わる時間が増え、それに伴い、赤ちゃんへの愛情がより深まりますし、父親としての自覚も育まれます。
また、赤ちゃんにとっても、自分を大切に扱ってくれて、お世話にしてくれるパパに、より愛着を抱きやすくなります。
私の夫は、1月ほど育休を取得し、その間、積極的にオムツ替えやミルクでの授乳、沐浴などをしてくれて、とっても助かりました。ただ、あまりにも、赤ちゃんが夫に懐いていて、私よりも夫に微笑んでいる気がして、ちょっとジェラシーでした💦
会社・社会の評価が向上する
最近では、国の支援などもあり、多くの会社で育休の制度が整ってきています。以前は、代わりがおらず仕事に穴をあけてしまう、育休開けで戻った時に席がないかもしれない、昇進や給料に影響が出るなどの理由から、育休を取りづらいケースが多々ありました。
しかし、最近では、そういったところが改善されつつあり、育休を取得することによるデメリットがなくなるよう取り組まれていて、法整備も進んでいます。
逆に、家庭を大切にしている人材として、高く評価する会社もあります。
また、育休を取得することで、仕事ばかりではなく、プライベートにおいても、周りの人に、家庭を大切にする人として良いイメージを抱いてもらいやすくなります。
人生を見直すいい機会になる
仕事をしていると、自分の人生をゆっくり見直したり、ちょっと立ち止まって考えたりしたくても、そんな時間を確保することはなかなかできません。
育児休暇は、育児のための休暇ではありますが、普段なかなか取得できない長期の休みを堂々と取得できる貴重な機会です。
もちろん、赤ちゃんのお世話や家事など、やることはたくさんありますが、仕事と違って、期限や時間に追われるようなことやプレッシャーがかかることはありません。
しばらくの間、仕事のことは忘れて、赤ちゃんや奥さんとの家庭での生活を存分に楽しみながら、これからの自分や家族の将来、ライフプラン、マネープランなど、一度見直してみるいい機会になります。
お金に代えがたい貴重な時間が得られる
子供が赤ちゃんでいる期間は、長い人生の中では、ほんの一瞬です。
すぐに成長して、保育園や小学校に通うようになります。24時間、毎日ずっと一緒にいられる期間って、実は、ほんとに貴重なんです。
成長してしまってからは、いくら欲しくても得られない貴重な時間ですから、少しでも、その時間を多くとって、愛しい赤ちゃんと、たくさんスキンシップをとりましょう。
男性の育児休暇制度について
育児休暇は、育児・介護休業法という法律で定められている労働者の権利です。
実は、勤務先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づいて、育児休業を取得することができます。もし、申請した場合、法律により勤務先は休業の申し出を拒むことはできません。
ただ、やはり、勤務先との関係をこじらせては、今後の仕事に支障が出てしまいますので、人事部署や上司などに早めに相談して、計画的に取得するようにすることが大切です。
男性の育児休暇制度には、国が定める以下の制度があります。
| 項目 | 産後パパ育休 | 育児休業 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 子どもが生まれてから8週間以内 | 子どもが1歳になるまで |
| 取得可能日数 | 4週間まで | 希望する期間 |
| 申し出期限 | 休業の2週間前まで | 休業の1か月前まで |
| 分割取得 | 2回取得可 | 2回取得可 |
| 休業中の就業 | 労使協定によっては就業可 | 就業不可 |
主に、産後パパ育休と育児休業があり、それらは、別々に取得できますので、最大で、4回に分けて、育児休暇を取得することができます。例えば、以下のような使い方ができます。
例1
子供が生まれてすぐに、産後パパ育休を4週間取得。その後、いったん仕事に復帰し、仕事の落ち着く時期を見計らって、1歳になるまでの間に、育児休業を4週間ずつ2回にわけて取得。(計12週間を3回に分けて取得)
例2:里帰り出産した妻と生まれた子供に会いにいくため、産後パパ育休を2週間取得。いったん仕事に復帰して、生後1か月の健診が終わり、里帰りから戻ってくるタイミングで、産後パパ育休の残りの2週間を取得。その後、仕事の閑散期を狙って、1歳になるまでの間に、育児休業を4週間ずつ2回にわけて取得。(計12週間を4回に分けて取得)
まとめて1年間の育児休業を取得するといった場合は、あまり関係ないかもしれませんが、忙しいパパにとっては、最大4回にわけて休業をとれますので、仕事の状況を見て、上手く分散させて休業することで、仕事と育児を両立しやくすなります。
育児休暇取得のデメリット
育児休業は、パパが育児に積極的に参加できる機会を与えてくれるとってもいい制度であり、取得すべき理由は最初にお伝えしましたが、逆に、取得することによるデメリットがないわけではありません。
収入が多少減る
育児休業は、あくまで休業ですので、その間の給料は出ません。
ただし、その代わり、国の制度で、育児休業給付金が支給されます。最大6か月間、育児休業前の賃金の67%が補償されます(7か月目〜12か月目は、50%)。
また、育児休業中は社会保険料が免除されますし、給付金には所得税がかかりませんので、手取り賃金で考えると、約8割の賃金が補償されることになります。
また、2025年4月の法改正で、「出生後休業支援給付金」という制度が新たに始まり、以下の条件を満たすと、さらに、給付率に13%上乗せされ、給付率は、合計で80%になります。(ただし、期間は、育休を始めた日から28日間のみ)
- 夫婦で14日以上育児休業を取得すること
- パパの対象期間:産後パパ育休中
- ママの対象期間:出産後8週間以内
※例外事項もありますので、詳細は国のホームページ等を参照ください。
多少育児休業前の給料よりは、下がりますが、家で家族と過ごせて、手取りで約8割の収入があるのなら、全然いい気がするのは、私だけでしょうか?
育児休業給付金+出生後休業支援給付金で、給付率80%の場合、手取りだと、ほぼ100%になるそうです!すごい!
ただ、ボーナスについては、算定に勤務日数が考慮されている場合は、その分が減額になる可能性があります。
退職金の加算期間から除外される
育児休業期間は、基本的には、勤務年数に算入されません。そのため、退職金の計算基礎となる勤務年数からは、多くの場合除かれることとなります。
逆をいえば、せっかく育児休業をとるのであれば、極力長い期間とった方が、お得とも考えられます。
育児休業期間が1か月であれ、1年であれ、どちらも勤務年数計算上1年が除かれるのであれば、育児休業給付金もあることですし、どうせなら割り切って、長い期間の休業を所得して、赤ちゃんとの大切な時間をいっぱいとってはいかがでしょうか。
理解の無い人・職場もまだまだある
育児休業が、かなり知られてきたとはいえ、人や職場によっては、まだまだ理解が得られない場合もあります。
それらの人等に、理解を求めるのは、なかなか難しいですし、長い時間がかかります。
そういったケースに遭遇した場合は、残念ながら、ご自身の考えや意思、今後のライフプランなどを考慮して、「選択」をする他ありません。
育児休業の取得を諦めるのも1つですし、法律を出して権利として育児休業を勝ち取るのも1つ、そういった考え方の相違は他の仕事の時でも影響してくる可能性が高いので転職するのも1つです。