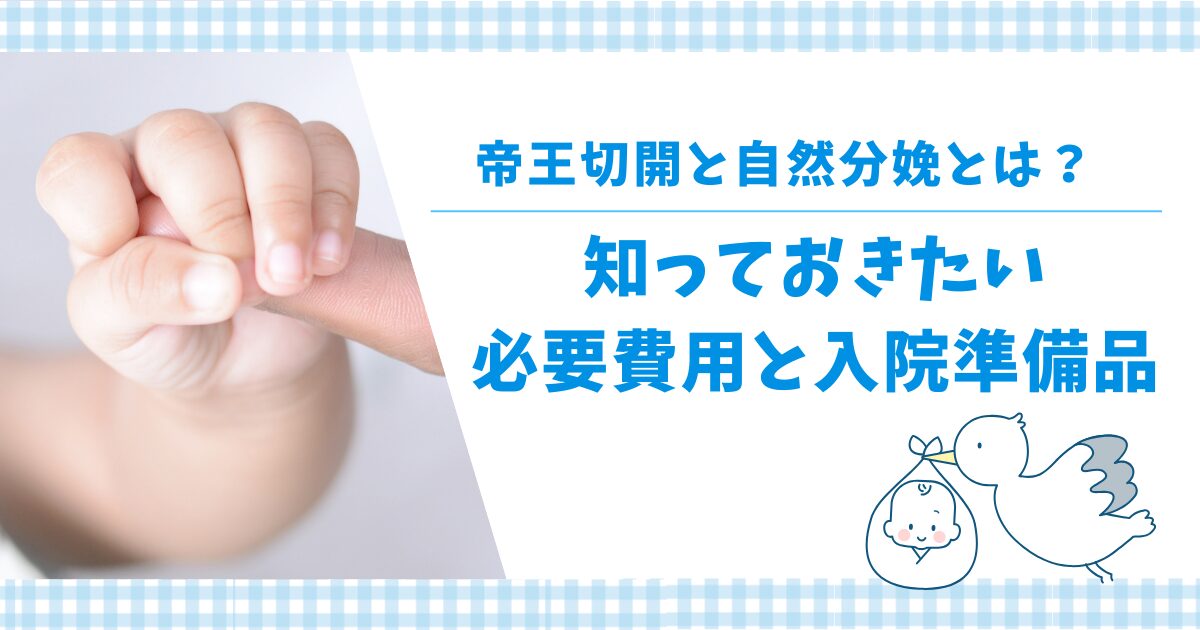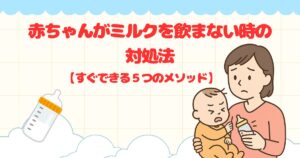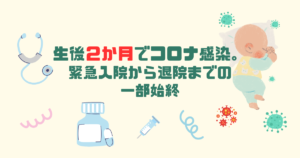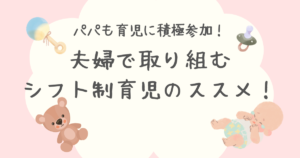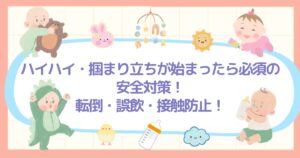こんにちは!なぎびです。
出産予定日が近くなってくると、赤ちゃんにもうすぐ会える!早く会いたい!といったうれしい気持ちの半面、出産に対する不安や生まれた後の育児に対する不安など、さまざまな気持ちが入り混じって、感情が不安定になることも多いと思います。
出産という未知の経験を控えたら、誰でも不安になるのは当たり前です。
この記事では、
- 帝王切開と自然分娩の違いは?
- 手術にかかる費用は?
- 手術に向けて必要な準備は?
などの疑問について、私の経験を踏まえて解説します。
帝王切開と自然分娩の違い
出産の方法には、大きく分けて、帝王切開と自然分娩の2つがあります。
ただ、実際の出産を、帝王切開と自然分娩のどちらで出産するのかは、基本的には自分で好きに選べるわけではありません。
赤ちゃんの胎内での状態(逆子、大きさなど)やお母さんの体調など、さまざまな要件を加味して、お医者さんと決定します。出産当日に、自然分娩から帝王切開に急遽切り替えることもあり得ます。
私は、自然分娩の予定でしたが、予定日の1週間前健診で、赤ちゃんの頭のサイズが予想より大きく、私の骨盤の大きさでは自然分娩では出てこれない可能性があり、母子共にリスクが高くなってしまったため、医師と相談の上、帝王切開で出産することになりました。手術室の予約の関係から、健診の翌々日に手術することになったため、大慌てで準備をしました💦
帝王切開とは?
帝王切開は、お母さんの下腹部の辺りを切開し、そこから赤ちゃんを取り出す方法です。
切開する場所や切開の向き(縦横)は、胎内の赤ちゃんの居場所を確認し、安全な場所で切開されます。
お腹を切開することになるため、術後は、患部がかなり痛みますし、子宮の収縮などの出産に伴う体の回復と、手術による傷の回復の両方が必要になるため、自然分娩よりも体力が元通りになるまでの期間が長くなります。
体がある程度元通りになるには、半年から、長い人では1年ほどかかる場合もあります。
また、術後は、看護師さんの助けがあるとはいえ、手術のリハビリと同時に、生まれたばかりの赤ちゃんの授乳やオムツ替えなどの慣れない作業を、お腹の痛みに耐えながらやらなければならないため、かなり大変だったことを記憶しています。
人によっては、産後何年も経っても、中のほうが疼くようにチクチク痛むという人もいますし、ぽっこりお腹がなかなか治らないといった話も多く聞きます。
私は帝王切開で出産しましたが、術中にかなり出血してしまい、あと少しで、危うく大学病院に緊急搬送されるところでした💦
麻酔から覚めて、その話を聞いてビックリ💦
帝王切開は、保険適用!保険金の請求を忘れずに!
帝王切開で忘れちゃいけない事は、帝王切開は手術扱いになるため、医療保険に加入されている場合は、多くの場合対象になります。
退院後、多少落ち着いてからでも十分間に合うので、診療明細書や領収書等はしっかりととっておいて、忘れず請求するようにしましょう!
自然分娩とは?
自然分娩は、自然な体の反応に従って、出産する方法です。
お腹の中の赤ちゃんが外に出てくる準備が整うと、いよいよ陣痛が始まります。
その陣痛の間隔が徐々に縮まっていき、破水し、出産するという流れになります。
陣痛が始まってから、赤ちゃんが生まれるまでの時間は、初産で12〜14時間程度、経産婦では6〜8時間と言われていますが、個人差がかなりあるため、参考程度と考えた方が良いと思います。
陣痛が始まったら、いつでも病院に行けるように準備を整えておきましょう。
予定日より遅れている場合は、胎内の赤ちゃんの状態によっては、陣痛促進剤(誘発剤)を使って陣痛を人工的に起こして、出産を促す場合や、帝王切開に切り替える場合もあります。
帝王切開・自然分娩にかかる費用
帝王切開は、保険適用になる分、必要な費用は、自然分娩に比べると安くなる傾向にありますが、入院期間が自然分娩よりも長くなるため、トータルでは、同じくらいの費用となる場合が多いようです。
私は公立の病院で、出産しましたが、手術費が20万円ほどで、新生児の管理や、入院にかかる費用(8日間入院)、術後の治療費等を加えて、トータルで約43万円でした。
健康保険の出産一時金制度が50万円ですので、持ち出しとしては、0円で済みました。
帝王切開、自然分娩に限らず、個人の専門医にかかって入院する場合やこだわりの個室やサービスを望まなければ、おおむね、健康保険の一時金の50万円以内で収まるのではないかと思います。
出産・入院に向けた準備
自然分娩、帝王切開に限らず、出産に伴い入院することになります。予定日1か月を切ったら、いつ出産することになってもおかしくありません!急な入院にも、対応できるよう事前に計画的に準備を進めておきましょう!
病院に持っていくものリスト
病院に持っていくものは、入院中に使う自分の身の回り品、赤ちゃん関係の用品、退院時用の用品、貴重品など、用途に応じて紙袋などで分けておくとよいです。事前に、しっかり分別しておくことで、入院中、あれこれ物を探す手間が軽減されます。
ただでさえ、出産で体力が落ちていますし、慣れない赤ちゃんのお世話もあるので、極力楽ができるように、準備をしておきましょう!
入院中の身の回り品
- フェイスタオル 2~3枚
- バスタオル 2~3枚
- 前開きのパジャマ
- ドライヤー(病室に無い場合)
- 産褥ショーツ 2~3枚
- 産褥パッド(L5~10枚、M15~20枚)
- 夜用ナプキン(1袋)
- 授乳用ブラジャー 2~3枚
- 母乳パッド
- 靴下 2~3足
- むくみ防止靴下 1~2足
- 肌着 2~3着
- 腹帯
- お風呂グッズ(シャンプー、リンス、ボディーソープ等)
- 洗顔グッズ
- 歯磨きセット(歯ブラシ、歯磨き粉)
- メガネ(コンタクト使用の人)
- 乳首ケア用のクリーム
- ティッシュペーパー
- スリッパ
- ブランケット・カーディガン等(体温調節用)
- コップ
- スプーン
- ストロー
- テニスボール(自然分娩の人)
- ビニール袋
- 洗濯物を入れる用の袋(紙袋等)
入院中の赤ちゃん関連用品
- オムツ(新生児用テープタイプ) 1袋程度
- ベビー肌着長・短(コンビ) 4~5着
- ベビー服(ツーウェイタイプ推奨) 2~3着
- 授乳クッション
- おくるみ
- ガーゼハンカチ 4~5枚
- 保湿ローション・クリーム
- お尻拭き
- 手口拭き
貴重品・文房具類
- 健康保険証
- 母子手帳
- お金(院内で日用品を買う用:1~2万円程度)
- 筆記用具
- 印鑑
- スマートフォン・充電器
退院時に必要なもの
- ベビー肌着(入院中用品と共通)
- おくるみ(入院中用品と共通)
- ベビードレス
- チャイルドシート(送迎車に取付)
- お母さんの私服一式(締め付けのない服!)
あると便利なもの
- ボディペーパー(入浴できない時用)
- ドライシャンプー(入浴できない時用)
- スマホスタンド
- タブレット端末
- 本
- 抱っこ紐(新生児から使えるもの)
病院によっては、パジャマやタオルなどをレンタルしている場合もあるので、活用すれば荷物や洗濯物が少なくて済みますし、衛生的にも安心です。
また、上記のリストにあげたものでも、病院側で用意してくれている場合もあるので、事前に入院先の病院に必要な物を確認しておきましょう。
今回記載したリストは、あくまで一例で、家族が定期的に洗濯物の交換や必要な物を届けてくれる場合を想定しているので、都合により、家族がなかなか来院できない場合は、もう少し多く用意する必要があるかもしれません。